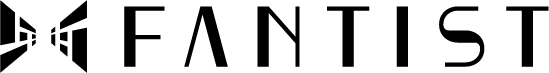“色彩の学び”を仕事に - 人気カラー講師が語る、資格取得後に「やるべきこと」とは?
2025/07/18

カラーコンサルタントである橋本実千代先生は、カラーセラピーやパーソナルカラーの個人カウンセリングを行う他、大学や企業で色彩教育の講師を務めるなど、色彩についてその奥深さを教える立場に幅広く携わられています。色彩を学ぶことで広がる可能性や、学びをどのように仕事に繋げていくかなど、たっぷり伺いました。
「色の面白さを伝えたい」がカラー講師活動の原点
ーー 講師として色を学ぶさまざまな場に関わられていらっしゃいますが、先生にとって「教えること」のモチベーションはどんなところにあるのでしょうか?
色の持つ面白さを伝えたいと思ったのです。色ってこんなに面白いのに、その魅力を知らない人がまだまだたくさんいる。私もかつてそうでした。色を活用すれば暮らしがもっと楽しくなる、今より生きやすくなるかもしれない、そんなことを伝えたい気持ちがスタートでしたね。だから、受講生さんから「なるほど」「やっとわかりました」「独学ではわからなかったことが、わかって嬉しい」とか、そういう言葉をもらえると、それがすごく嬉しくてやりがいになっています。
ーー橋本先生はFANTISTで2つの講座を監修されていますが、FANTISTにはどのような特徴があると思いますか?
今、対面だけでなく、大学機関などzoomや動画配信の依頼も多くなっています。そのような流れの中で、FANTISTさんはとにかく動画が綺麗ですよね。「やってみたい」とモチベーションが上がります。それにレッスン数が6回などちょうど良い回数にまとまっているところも、受講される方のニーズに合っていると感じます。
また、受講期間が設けられているところもポイントです。期間が決まっていないと「いつでもできる」と受講を先延ばしにしてしまうケースもあるので……自分がそうなのですが(笑)。一定期間の中で受講をする仕組みも、FANTISTさんならではの魅力ではないでしょうか。

そしてやっぱり、学生なり社会人なり日々忙しい方も、自分の好きな時間に好きなペースで学べることですよね。移動のための交通費もかからないですし。内容も分かりやすいし、質問にも答えてくださるしというところがメリットだと思います。
ーー 橋本先生は、どのようなきっかけでカラーについて学ぼうと思われたのでしょう?
元々洋服が好きで、はじめはテキスタイル卸売業と呼ばれる洋服の生地の会社に就職しました。広くいろいろなアパレルブランドに触れられる点に魅力を感じて入社しましたが、働きながらどこかでいつか洋服の販売の仕事もしたいと考えていました。そのような時に「似合う色」というものがあると聞いて、興味を持ちました。パーソナルカラーのメソッドって、1980年代にアメリカから日本に入ってきたもので、当時はまだ広く知られていなかったのです。
ただ、コーディネーターさんによって「あなたは春です」「秋のグループの色が似合います」と、違う意見を話すのを聞いて「なぜこういうことが起きるんだろうか?」と疑問に感じて自分でもきちんと学んでみたいと思いました。最初に学んでみたのはカルチャーセンターのようなところの全20回ほどの講座でした。

同じ頃、社内に色彩検定(※)の2級まで取得していた女性がいて、「橋本さんもやってみたら」と教科書を貸してくれたのです。当時は公式テキストがなく、スクールで個別に作っているテキストや参考資料があるだけだったのですが、勉強してみたら面白くて。3級と2級を併願して合格し、次の冬には1級にも挑戦して合格できました。当時の合格率は15%ぐらいだったので、正直なところ落ちたと思っていたのですが、まさかの一発合格でした。
(※)文部科学省後援の公的資格で、色の専門知識と技能を証明する資格
難関「色彩検定1級」に合格し、人生を変えることを決意
ーー それは相当勉強されたのでは? 当時から色の学びを仕事にしたいという想いがあったのでしょうか?
はい、かなり勉強しました。色の専門部署から異動のお誘いもありました。当時は、いわゆるSPA(「製造小売業」、ファッション商品の企画から生産、販売までを自社で一括して担うビジネスモデル)と呼ばれるZARAやH&M、ユニクロが広く知られるようになる以前ではありましたが、生地の卸売業界が先細りになり始めていく過渡期の時代でした。
その市況を見ながら「この会社に定年までいる未来が想像できないし、ここで動こう」と。そこから本格的にスクールを探し始めて、当時からカラーコンサルタントとして活躍されていた高坂美紀先生が講師を務めるスクールに出会いました。検定取得ではなく“プロを育てる”ことに重きを置いた講座内容で、「実質的に仕事に結びつくのはこの先生のこのコースだ」と思い、11年間勤務した会社を辞めました。毎週3時間、1年間で72万円という金額でしたが、退職金を使って受講しました。

ーー それは思い切りましたね……!
色彩検定1級には受かったけれど、「さあ、じゃあ私に何ができるの?」と思った時に、ただ級を取っただけで何にもできない自分がいて。ここから知識を“血と肉”にしていこうと。ですから、1級を取得してからが面白かったですね。
ちょうどその年、色彩検定協会が、講師を育成するための「講師養成講座」というものを始めたタイミングだったので、こちらも土日を使って受講をし、色彩心理を学べる学校にも通いました。もうこの一年は学びの年にしようと決めましたので、火曜日は高坂先生の講座、木曜日は色彩心理、その他にもアロマテラピーやイタリア料理など、全曜日をインプットの時間で埋めました。
ーー その後、どのように学びを仕事に繋げていったのでしょうか?
色彩検定協会の「講師養成講座」の同期生だった3人で仕事をしようということになり、新宿の事務所を借りたのです。うち一人が出資をして、残りの私たち2人は従業員として働く形で、そこで細々とカラースクールを運営するところから始まりました。飲食店のウィンドウディスプレイやパーソナルカラーなども行いました。

私は同時期、自分が卒業したカラースクールで非常勤講師を勤めていました。最終的に事務所は解散したのですが、私は同じタイミングで非常勤から専任講師になって、今も籍をおき続けています。
現在はスクールで企画やイベント講師の仕事をしながら、本を書いたり個人で請ける仕事をしています。起業して完全に一人で、というよりはこのように企業の仕事にも関わりながらの方が私には向いてると感じていて、この働き方をしています。
色彩資格を仕事にしたいなら、積極的に発信を
ーー 「色」を活かせる業界や仕事はまだ大きく可能性がありそうですね。
受講生の方からよく聞かれるんです。「先生、色彩検定で資格を取ったら仕事になりますか?」と。でも、どんな資格もそうですが、資格を取っただけで急に仕事になるわけじゃないですよね? 司法試験に受かっても、いきなり仕事がバンバン来るわけじゃない。「活かすも殺すも自分次第です」という話をしています。
例えば私の場合は、2級を取ったときに「せっかくだから仕事に活かしたい」と思っていたら、地元の区報に「東京都で初めての『色彩景観ガイド』を作る」という記事が載っていたのを見つけたのです。「区民の皆さんから意見を募集します。景観について思うことを書いてください」と。そこで「京都のような観光地ではないけれど、ある程度の色使いの決まりは必要であろう」といったことを書いて送ったら、採用されまして。バスで区内を回って写真を撮ってそれをレポートにまとめたりするような活動内容で、面白かったですね。
これが私にとって色の知識を活かした最初のお仕事でした。一回の会議ごとに3,000円いただけたのがとても嬉しかったです。色の資格がお金になったのですから。受講生の皆さんには、日々アンテナを張ること、自ら行動することの大切さを伝えたいですね。
ーー 今後、ご自身として色の分野でどのようなことをしていきたいと考えていらっしゃいますか?
私は20代前半で腎臓が悪いことがわかって投薬治療をしていましたが、37歳で人工透析治療が必要になってしまったのです。現在は移植手術をして透析はしていませんが、何度も経験した入院中は、具合の悪さによって色の見え方が変わったりして「色って面白いな」と思いました。これまでに色が関係する「光線療法」や、「レインボー療法」という色を使った痛くない針治療のような方法を試してみたりもしました。色のパワーを、自分の病気を通しても体感するようになりました。
元々は「洋服の色選びのアドバイスをしたい」というところから始まったのですが、病気の経験を通して、障がい者の方などに、色を使うことによって癒しの効果やこんなに面白いことがありますよということを伝えたいと考えるようになりました。地元の患者会でも色のお話をするようにしています。

学生にもカラーユニバーサルデザイン(色覚の多様性に配慮し、誰にとっても情報が正確に伝わるようにデザインすること)の話をすると、すごく反応が良いのです。「もっと知りたい」と思ってくれる学生も多くて。そういった、まだあまり知られていない世界を伝えていきたいと思っています。
あとは、お子様向けにも何か発信をしていきたいと思っています。ちょうど今、出版社さんと子ども向けの色彩の本を作っていて、今年の11月発売を目指して進行中です。
ーー 最後に、これから色彩について学ぶ・今学んでいる受講生に向けて、メッセージをお願いします。
色彩について学ばれたら、ぜひ日常の中で活かしていってください。また仕事にしていきたいと思われたら、その学びや興味について発信していく行動力が必要だと思います。せっかく勉強したのにそのままでいたらもったいないですし、それを外に向けて発信していかないと繋がらないので。あとは、日本色彩学会などに、環境色彩研究会、パーソナルカラー研究会など、さまざまな研究会があるので、そういった学びを続けていけるところに所属をして、いろいろな先生方や仲間と関係を作ることも大切です。
そうして繋がった人とのコミュニケーションにおいては、自分が得することばかり考えるのではなく、その人のために何かしてあげたいという気持ちを持って接することをぜひ心がけてください。人と人として繋がることができた相手とは仲間として一緒に仕事ができたり、何かのタイミングで声をかけてもらえたりすると思いますから。
プロフィール
橋本実千代
カラーコンサルタント。 色彩検定協会認定色彩講師(UC級講師資格保持) テキスタイル卸売業に11年間勤務後、大学や専門学校、企業、個人向けに色彩講座・コンサルティングを実施。テレビ、ラジオ、雑誌、新聞の連載等でも活躍。FANTISTでは「はじめての配色・カラー入門コース」と「FANTIST認定『カラーセラピスト』資格講座」の2講座の監修を務めている。
橋本実千代先生に学ぶ
はじめての配色・カラー入門コース
「カラー」の基本知識と実践スキルを習得できる入門コース。明度、彩度、色相などの配色の基本から、色の特徴や心理的効果、自分でイメージする色選びができるようになるための配色方法まで、幅広く学ぶことができる。
 レッスンを見る
レッスンを見る